4-2Reichsluftfahrministerium (RLM:航空省)
WW2開始以降
WW2開始以降1944年までは細かい移動や、組織の
新設のみで大きな組織変更は有りませんでした。
RLM全体としてみると、作戦を受け持つ
Generalstabと、生産、補給、管理を担当する
Staatssekretaer引き続き分かれていた為、権限
が重複、分散して停滞を招きました。
中でも大きな問題は、GLで進められる航空機の
生産と新機種の選定に対してGeneralstabの
意見が十分に反映されない状態が続いたこと
でした。
以下、年別に動きを紹介します。
☆1939年
開戦後間も無くの1939年10月1日に
補佐的な役割の、General z.b.V. beim
Staatssekretaer der Luftfahrt und
Generalinspekteur der Luftwaffeが設置され
ここでInspektionに対する直接命令を行う事
になりました。
☆1940年
戦争の進行に伴いGeneralstabを始めとする作戦
立案部門が実戦情報をInspektionから直接迅速に
入手すること重要になり、関連する組織変更が
続きます。40年1月6日にInspektion4が
Ob.d.L.に直属する高射砲部隊の責任者である
General der Flakartllierie beim Ob.d.L.の
所属となりました(この時Inspektion13も移
ったという説もあります)。
また1940年4月に1,2,3,8,12の各Inspektion
はChef des Generalstabに直接報告を行うこと
になり、実質的な所属変更が行われました。
同時にInspektion5,6,14はChef der Luftwehr
に、Inspektion7は
Chef des Nachrichitenverbindungswessen
の所属となりました。同時にInspektion15
はLuftvereidigungszone West(西部方面担当)
の編成に伴ない、休止状態となり、任務の
一部をInspektion4に引き継ぎました。
1940年4月1日付けで新しく海上救助を
任務とするInspektion16も設けられました。
(Battle of Britainも意識したのでしょうか
?)
Inspektion11(空挺部隊)は5月迄に廃止
され、この分野の監察はStudentが指揮する
XI.Fliegerkorpsの任務となりました。
☆1941年
1月31日付けでInspektion12が廃止されて
その機能は、Inspektion2(爆撃機)に引き
つがれました。航法は爆撃作戦に関係の深い
分野であり、合理的な統合だと思います。
夏以降、Inspektion1-3はGoering直属
の職務となり、権限が拡大されました。
それらの正式名称は以下の通りです。
General der Aufklaerungsflieger(L.In.1)
General der Kampflieger(L.In.2)
General der Jagdflieger(L.In.3)
これらは任務の具体的な遂行に関して当然
Chef des Generalstabと密接な関係を維持し
ました(L.In.1に関してはChef AWに属した
と言う説もあります)。
また、空軍組織内のランクは、Division
Kommandeurと同格とされていました。
これらをサポートする事務部隊は「監察局」
に当ります。
RLMの最も大きな問題だった航空機生産の遅れ
がこの時期から露呈し。航空部隊の定数に
対する配備率の低下に繋がりました。
1939年9月には98.9%だった配備率は戦局の
進行と共に低下して、41年12月には
63.3%となりました。特に爆撃部隊はこの時期
47.1%まで落ち込み、更に稼動できたのは僅か
にこの51%に過ぎませんでした。
主な理由はUdetが率いるGLが機能しなかった
事ですが、Goeringは、6月20日付けで
Milchに対して航空機生産を4倍にするプロジ
ェクトの進行を命じました。Milchは生産
工場の統合やGL内の改革を進めようとしま
した。このことが11月16日のUdetの自殺に
繋がり、その後Milch自身がGLMに就任して
生産向上を図りました。
この間のMilchの動きに付いては、彼がUdetの
上司に当るにもかかわらず、対応が遅れたと
言う批判があります。1939年にUdetが航空機
生産の責任者になった以降、隠れた確執が
続いたようで、双方に問題が有ったと言わ
ざるを得ません。
☆1942年
42年2月15日にSpeerがReichsminister fuer
Bewaffnung und Kriegsproduktion(軍需相)に
就任し、GLが担当する航空機生産体勢にも影響が
生じました。
Speerは部品の共通化や命令システムの合理化、
資源、労働力の配分の見直しを通じて、生産高
の向上を図りました。RLMは生産計画の立案は
行うものの、実行に際して必要な資源の配分の
権限を持つ軍需省が実質的に生産高を支配しま
した。この時からMilchも航空機増産の目的で
Speerに積極的に協力したことが知られています。
1942年4月に海上作戦を担当のL.In.8が廃止
され、任務がGeneral der Luftwaffe beim Ob.d.M.
に引き継がれます。(この時期にLWで航空魚雷
の実戦配備が始まったことを付記します)。
この後戦局への具体的対応策が続きます。
1942年6月に建設や航空機生産担当のInspektion
17が設置されます。正式名称はInspektion fuer
Luftwaffenbautruppen und Kriegsgefangeneと
言いました。Kriegsgefangeneは戦争捕虜を意味
し、東部戦線における大量の捕虜の労働力を
生産や建設に有効活用しようとしました。
42年12月に空挺部隊を地上戦に積極的に活用
する目的でInspektion18(Feldverband)に
FliegerkorpsXIII司令官のE.Meindlが任命され
ました。
☆1943年
連合軍の爆撃が本格化した1943年に入り、ドイツ
本土防衛上の効果的な組織運用の為、
航空部隊だけでなく地上組織も再編成されました。
作戦部隊の移動を管理するInspektionr5が5月に
廃止され、任務は、General der
Fliegerbodenorganization und des Flugbetriebs
(GendFlbouflugb)に引き継がれました。
また43年中にGeneralstab傘下の技術責任者と
してGeneral fuer Truppentechnikが、また
部隊管理を担当するChefintendant der Luftwaffe
が設置され、これらは組織的に何れも
Generalquartiermeisterに所属しました。
この変化は、国内が航空戦の実質的戦場と化した
為、従来は本国の管理任務とされていた分野を、
実戦担当のGeneralstabが直接関わるように
なったと見る事ができます。
2月にはStalingrad補給の失敗が有り、
HitlerのLWに対する信頼は大きくゆらぎました。
搭乗員の訓練体勢の見直しの為1943年3月1日
L.Ins.9は廃止され、5月1日に設立されたGeneral
der Fliegerausbildungsに任務が移行しました。
更に1943年5月1日に全ての輸送機を管轄する
XIV.Fliegerkorpsが編成され10月に指揮官の
J.CoelerはOb.d.L直属のGeneral der
Transportfliegerとなりました(実質的に
Genst Quに所属)。
8月17-18日のPeenemuendeのV兵器研究所
爆撃の直後Chef der GeneralstabのJeschonnek
は拳銃自殺を遂げます。
実戦部隊においては9月1日付けでGeneral der
Schlachtfliegerが任命された事と9月15日付け
でI.JKps及びII.JKpsが編成されたことを付記します。
☆1944年
連合軍の空襲は一段と激化し、1944年3月1日に
RLMと軍需省の協同組織として戦闘機生産の計画と
実施に責任を持つJaegerstabが作られました。
これは他機種の生産にも影響を与え、軍用機生産
の権限が大きく軍需省に移った事になります。
しかしこの後もHitlerは英国に対する爆撃の意思を
継続し軍用機の生産計画に影響を与えました。
5月23日の会議でMilchがMe262の使用方法を巡り
Hitlerと対立して実権を失いますが、期を
一にして戦局の変化への迅速な対応の為、RLM
M内部の見直しがありました。組織は大きく
三つに集約され、各分野の責任者がGoeringの
代理権を持ちました。
一つは主に人事分野を担当するChef der
personallen Ruestung und NS-Fuehrung der
Luftwaffe(略称:ChefPersRuestuNSFue。
NSはNationalsozialistischの略)です。
NS-FuehrungはNaziの思想を下に統制を図る
為に各軍の内部に設けられた組織でしたが、
人事部と一体となったことは、裏を返せば戦局
の悪化に伴う士気の低下の深刻化を意味します。
また戦意高揚の目的で褒章を任務とするChef
fuer Auszeichnung und Disziplinarsachemnが
1944年8月1日付けで設置されました。
第二はChef der Generalstabであり作戦面
全体を統括しました。また、通信担当のChef
der Nachrichitenverbindungswesensの重要
度は一段と増して実質的に独立した地位を
有しました。
技術分野の責任者がこの時期以降Generalの
呼ばれる事になった為、Chef NVWは4月11日
以降、Generalnachrichitenfuehrer der
Luftwaffeと呼ばれ、形式上はChef der
Generalstabの所属でした。
LWの上層司令部を総称するOKLという名称は
(Oberkommand der Luftwaffe)、
ChefPersRuestuNSFueとGeneralstabを総合した
呼び方としてこの時期以降初めて用いられた
ものです。
第三はRLMの管理分野で、新設のChef der
Luftfahrtの管轄となりました。
これに伴いChef der Luftwehrは44年7月
31日付で廃止されました。
これ以外にOb.d.L.には高射砲や建設担当の
重要な独立した責任者が直属していましたが、
これらは便宜的にChef des Ministeramtes des
R.d.L.u.Ob.d.L.の所属とされました。
この変更を概観するとで、Generalstabは
単独で作戦面の責任を持つ事が初めて
明確になりました。しかし一方で
ChefPersRuestuNSFueに就任したのが
Goeringの側近であるBruno Loerzerであり
、Goering自身の影響力の回復策である部分
が否定できません。
結局、人事に代理権者を置く組織は迅速な
運用が困難であり、ChefPersRuestuNSFueは
12月20日に廃止されて、人事権はOb.d.L.に
戻されました。
6月6日の連合軍のNormandy上陸後、Goeringの
威信は全く失われました。1945年6月20日には
StとGLMが正式に廃止されてMilchが
(Generalinspekteurの肩書きは保持したものの)
実質的に組織から除外されました。この後
Speer自らの提案も有り軍用機生産は完全に
軍需省の管轄となりました。
GLMの人員はChef der Technischen Luftruestung
の下でGeneralstabに所属しました。
連合軍に対抗するため、航空部隊の移動や
機種の更改は一層頻繁となり、GendFlBOuFlugb
の任務は再度見直され、部隊移動は1944年6月
27日創設のInspekteur der Fliegernbodenorganisation
und des Flugbetribesが専任し、9月25日からは
装備補給等の分野をAbteilung
Luftwaffenbodenorganisationが担当しました。
また乗務員養成の促進の為1944年7月1日に編成
されたLuftflotte10が、訓練部隊に対する
装備補給を担当しました。しかし物資の不足と
補給の困難は深刻で訓練部隊の強化は殆ど
不可能になっていました。
8月から航空機の整備力を改善するために
Chefingenieur der Luftwaffeが創設され、
整備部隊に対する指示を統括しました。
1944年組織図
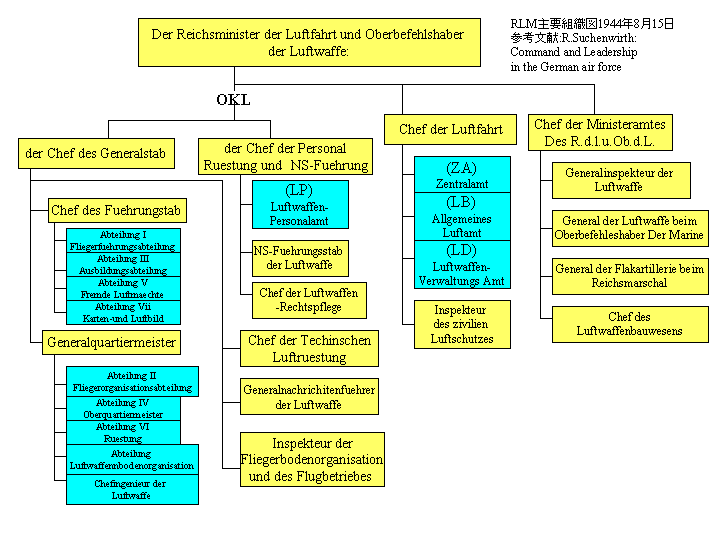
戦局の悪化に対する対応が続きましたが、
根本的な事態の改善策は無く、状況に
対して常に後手の対応の感は否めません。
7月20日のHitler暗殺未遂事件でLWはまたもや
Chef der Generalstab(Korten)を失い、
曲折の末Kreipeが後任となります。
この後SSによる内部監視が強化され、不正蓄財を
理由として処刑につながった例も出ました。
Hitlerの方針に反対する公の議論は許されず、
RLMとLWはNazi党に追従して行きます。
8月24日に連合軍によりパリが解放され、
敗勢は明らかでしたが、44年秋から戦局の
挽回を図る目的でGoering直属の特定分野
責任者が次々と任命されました。
9月30日にはGeneral der Waffen-SSのKammler
がInspekteur ueber alle durch Raketenantrieb
ausgestatteten Kamphmittel der LW. bis zur
Truppenreife(ロケット推進兵器全体の監察責任者)
となり、この分野の権限をSSが握りました。
12月11日にはHitlerの特別指令に対応する
部隊を組織する目的で、Stab fuer
Sonderauftraege und Truppenvorschlaege
にFeld-Divisionの司令官の経歴を持つ
Olibrichが就任しました。
この時期にはHitlerはGoeringとLWに対して
信を置かず、作戦はHitler自身の思いつき
に支配されました。
☆1945年
予備役だったKammhuberは1945年2月2日に
Ob.d.l.直属のSonderbeauftragter fuer
die Abwehr viermot Kamph-verbaende
(4発爆撃部隊対策特別委員)に任命され、
更に3月17日にGeneralbevollmaechtigter des
Reichsmarschalls fuer Strahlflugzeug(
ジェット機総代理権者)となりました。
民間の防空組織はそれまで、L.Ins.13
(指示連絡)及びArbeitsstab Luftschutz
(企画立案)が共同して管轄していましたが
Hitlerの意思により、1945年初め(時期詳細
不明)に、Chef der Luftschutzの下で
両部門が統一されました。
1945年3月26日にも組織変更が有り、権限
はChef der Generalstabに一層集中して
、これまでの苦い経験を生かした戦争
遂行に適した組織となりました。しかし
英米軍が既にライン川を越えた時点での
変更は徒に混乱を助長しました。
またこの時期にはRLMおよびOKLの主要組織
はBerlin近郊から中央ドイツのWeimarに
移動しましたが、再び危険が増大した為
、3月末からオーストリア国境に近い山岳
地域への再集結を開始しました。この間に
大量の文書が散逸したとされています。
1945年組織
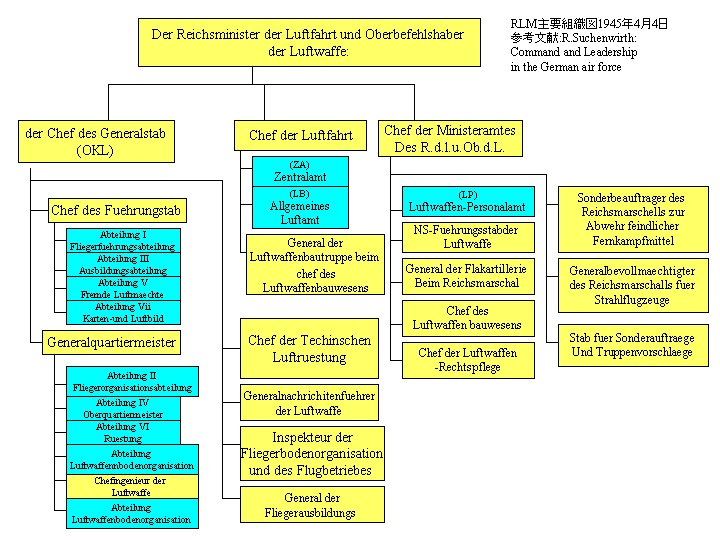
連合軍は更に侵攻して中央ドイツを挟撃し
ました。東西に分かれていた軍区が圧縮
された為、Hitlerは、OKWの参謀本部を
OKW/Fuerungstab"A"(Nord)と"B"(Sued)に
分けて両地域で単独作戦行動が執れる
よう変更し、1945年4月15日付で北部司令官
(Oberbefehlshaber)として海軍のDoenitzを、
南部司令官は当時西方軍司令官だった
Kesselringを発令しました。
対応してOKLの組織が二つに分けられ、OKL
NordとOKL Suedと呼ばれましたが、上述の
ように殆どのRLMとOKLの組織は南ドイツに
移動してOKW"B"(Sued)の担当区域内に有り、
OKL NordにはFuehrungstabの一部と連絡
スタッフ(Luftwaffenvernbinding Nord)だけが
残りました。また当初は南から北への命令
系統の確立が予定されましたが、末期に
使用できた連絡手段は一本の無線回線だけで
した。
ここでGoeringの辞職事件が発生します。
Hitlerは4月22日に脱出を放棄し、Berlinに
留まることを決意しますが、Goeringは4月20日の
Hitlerの誕生祝賀会に出席した後、Obersaltzburg
に戻ってこの情報を入手し、Hitlerが国家元首
の職務を停止したと判断して23日の15時に、
(1941年9月29日付けのGoeringをHitlerの後継
と定めた法令を根拠に)Hitlerに打電して地位
を継承する許可を求めました。
これにHitlerは激怒し、彼は即日Goeringに
自発的辞職を命じた上で軟禁し、4月25日付けで、
後任Ob.d.L.にvon Greimを任命しました。更に
4月29日付けで、Goeringはナチ党籍も剥奪され
ました。
SSはこの後も彼の処刑を企みましたが、5月5日
にこの事を知ったKesselringが正式にこれを
禁じたのでGoeringは生命の危機を逃れました。
Hitlerの死亡一週間前の土壇場のこの事件
は、Bolmanの策略だったと言う説があります
が、何れにしてもHitlerの信任を失っていた
Goeringに後継の可能性は有りませんでした。
RLM/OKLは南ドイツに分散して通信手段を失っ
たまま最後の時を迎えます。ドイツ全土で
約3500機の軍用機が残っていたとされていま
すが、燃料補給や指揮系統は無くなっていま
した。
4-3Technische Amt (LC:技術局)
WW2初期から中期
Luftwaffeの技術開発を統括していたLCの重要度
は言うまでも有りません。ここではWW2中期まで
の概略を御紹介します。他の資料を見る際の参考
になると思います。
既にご紹介したようにLCは1933年のRLMの設立
直後から独立部門として存在しました。
研究:Forschung,開発:Entwicklung,購買:
Beschaffungの3部門を有し、1934年中に組織
の整備が進みました。与えられたミッション
として、全てのLWの装備の開発、購買をLA、
企業側、陸軍と協力して進めるよう取り決めら
れました。
1934年時点でのLCの組織を以下に示します①。
Chef-Ing.P 技術者と地上支援要員の管理.
Abteilung Forschung:LCI
研究機関に対するプロジェクトの割り当て。
Abteilung Entwicklung:LCII
a.航空機、エンジン、機体装備、通信機器
爆弾、火器、弾薬等の開発プロジェクト
の企業に対する割り当て。
b.開発製品の採否の決定及びテスト機関の運用
Abteilung Beschaffung:LCIII
a.航空機、エンジン、装備等の購買
b.プロジェクト進行状況の監督
c.企業育成の計画立案
d.企業育成プロジェクトの監察
e.企業側監督者(Beautragter fuer
Industriepersonal)の指導
Abteilung Haushalt:LCIV
a.LC全体の予算管理
b.企業に対する発注書の正式発行
この時期は研究、開発、購買と内部機能を分割
して横割りで担当していたことを特徴としま
す。
この分担は1938年に見直されて、航空機、エン
ジン等ジン等の分野別の縦割り組織に改変されま
した。参考文献よるとこの時点では13の分野に
分けられたとされています。
また1939年2月1日付けで、LCはGLM(Genralluftzeug-
meister)に所属しました。1939年12月12日付けの
組織として以下の8項目の兵器種に分けられていま
した②。
Abteilung Forschung:LC1:研究
Abteilung Flugzeug :LC2:航空機
Abteilung Triebwerk:LC3:エンジン
Abteilung Funk und Navitationsgeraet:LC4:通信、航法装置
Abteilung Ausruestung:LC5:機体装備
Abteilung Waffen und Munition:LC6:火器と弾薬
Abteilung Abwurfmunition und -einrichtungen:LC7:爆弾
Abteilung Bodengeraet:LC8:地上装備
GLMをUdetの死後Milchが引き継ぎ、この後1942年の夏以降、
局内でもう一度購買機能の分割が有りました③。
開発関係の部をGL/C-E、購買関係の部をGL/C-Bと呼び、
番号は上記に一致したようです(つまりGL/C-E2は
航空機開発部です)。また新しく、Abteilung Werkstoffe
GL/C-10:原材料担当が新設されました。迷彩の標準は
ここから発行されていたようです。
これ以降、1944年6月のGLM廃止後の動き等が注目される
のですが機会を改めたいと思います。
最後にChef des Technische Amtの一覧を上げておきます。
Wilhelm Wimmer 1933年から1936年5月31日
Ernst Udet 1936年6月1日から1941年11月17日
Wolfgang Vorwald 1941年11月から1944年9月1日
①参考文献8 P46-47
②参考文献9 PXXVII
②参考文献9 P8
お気づきの点があったらご連絡下さい(直)。
ホームへ戻る