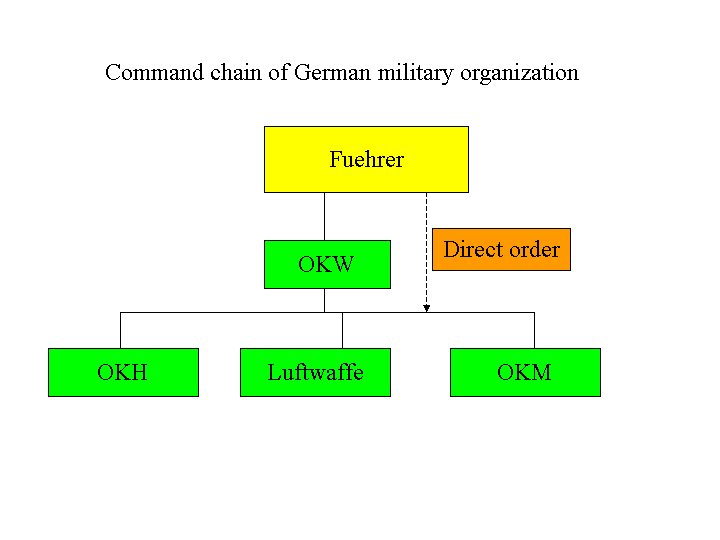Luftwaffe Foundation and Organization
(03年03月08日:青字はNEW)
by N.Dejima
内容の多くを
「The Luftwaffe,1933-1945 by Michael Holm」
から作者の了解の下に引用して
います。大変感謝しています。
Many items are quoted from
"The Luftwaffe,1933-1945" by
Michael Holm under his
permission.
Thank you very much for
his kind coopration.
また参考文献をご参照願います。
1.ここ有りません
2.陸軍との協力について
2-1.Luftwaffeの性格
WW1におけるドイツの航空戦力は陸軍に所属していました。
Nazi政権下の独立空軍設置の一つ理由に、戦力の集中によ
る効率化が有り、またその作戦理念は他の戦力(陸軍、海
軍)と協力の下で最終的な戦争の勝利を獲得することでし
た②-1。従って設立当初からLuftwaffeは陸軍と共同して
行動する性格を内包していたと言えます。
Luftwaffen-kommando4の指揮官だったDeichmannによれば
具体的な作戦行動の規範として1935年にLuftkriegfuerung
No16が発行され、その後度々の改定を経ていました。
2-2.陸軍協力偵察部隊
☆発展
1930年代中期に、陸軍で戦車部隊の配備が始まり、効率的な
運用の為に戦場の航空偵察による情報の活用が重要視されま
した②-2-1。部隊レベルによる空陸軍の共同作戦の訓練を経
た後、1937年7月1日にはOb.d.L直属のder Generals der
Luftwaffe beim Oberbefehleshabers des Heeres(GendLwbObdH:
陸軍総司令官付Luftwaffe将官と呼ぶのでしょうか)が任命さ
れました。(別項の組織図をご覧下さい)。
その任務はOb.d.H.に対する助言及び、Lwに設けられた陸軍
協力航空隊(1938年以降配備)の統括であり、興味深い事に
戦時にはOb.d.H.の命令を受ける事になっていました②-2-2。
開戦時のGendLwbObdHは1939年2月1日に任命されたRudolf
Bugatschでした。また彼はInspekteur der Aufklaerungsflieger
として偵察機部隊全体の監察任務にも就いておりLwがdas Heer
(陸軍)との関係を極めて重視していたことが分かります。
GendLwbObdHの下に運用責任者として
Kommandeure der Luftwaffe(Koluft)が、
GeneralstabのGeneralmajerもしくはOberst級
から選任され、Heeresgruppe及び重要な
Armee毎に置かれました。このシステムは
1942年迄継続します。
Koluftの任務には各部隊の指揮の他、配属
された高射砲部隊の指揮、空軍を代表して
陸軍司令部との協力方法の検討を行う事や、
Luftflotteに対して攻撃部隊の参画方法の
具申を行う事があり、航空支援の要となる
ポジションでした。従って平時から陸軍と
の信頼関係を築くことが重要とされていま
した。②-2-3
KoluftはLuftflotteとは別の組織であり、
(H):近距離偵察staffel、(F):長距離偵察
Staffelから成っています。一人のKoluftに
1から9個Staffelが所属しましたが、これらは
Lwの組織上は原隊のAufklaerungsgruppeから
分遣された形式をとっていました。
部隊の配備状況が、The Luftwaffe,1933-45
の関連ページに紹介されています(例は
1939年9月1日時点です。ページの下の
方を見て下さい)。
またArmeekorp毎の(H)および(F)の配備状況
が下記に公表されていますのでご参照願い
ます。
http://chrito.users1.50megs.com/kstn/okh/1sept1939.htm
その任務には、戦術偵察の他、戦場偵察
や砲兵部隊と連携した着弾偵察が含ま
れました。1939年時点で殆どのArmeekorp
毎に1個Staffelが割り当てられ、全体で
30個を数えました。
更に対ソ連戦が開始する時点で、それとは別
にPanzerdivision(機甲師団)毎に約20個の
Aufklaerungsstaffel Panzerが割り当てられ
ていました②-2-4
これらの部隊の作戦行動は陸軍の意向に
基きましたが、Deichmannは航空機の運用は
使用する機種、搭乗員の技量、天候等に大
きく左右され、他の兵種に比べて専門性が
高い為に、Lwが運用したと述べています。
従って陸軍から必要なMissionの連絡を
受けた後の行動計画の立案は、Lw(部隊)
に任されました。②-2-5
専門能力を買われて空軍から陸軍に出向と
言う感覚だったのではないでしょうか。
☆作戦行動 ②-2-6
戦術偵察の主要任務は、前線の敵の陸軍部隊
の配備や動向に関する情報収集ですが、移動
の早い機械化部隊を追尾する場合は、複数の
偵察機間で任務を受け渡して航続力の不足を
補う方法がとられました。地上での戦端が開
かれると戦場偵察に移行し、戦況に関する情報
や特定区域の敵の地上戦力の位置、砲兵部隊
や予備部隊、機甲部隊の動きに関する情報収集
を行いました。また自軍部隊の位置や進撃速度
の確認も重要な任務でした。砲兵部隊に協力
する着弾観測の任務は二つに大別され、一つ
は正確な敵部隊の位置に関する情報の収集、
もう一つは着弾修正及び砲撃の効果の確認で
した。自軍砲兵部隊の速い展開に合せて、
Staffelの指揮官は無線通信を用いて陸軍の
司令部からの指示連絡を受け、適切な行動を
判断して搭乗員に対して指示を出しました。
陸軍にとって長距離偵察機の任務は広い
地域にわたる敵地上部隊の配置・移動の情報
収集であり、敵の反撃の規模や時期を予想
する為にも重要な意義がありました。従って
飛行ルートの多くは敵軍の移動が行われる鉄道
や主要道路に沿いました。
担当偵察区域は直接協力する陸軍部隊の担当
地域と一致することが原則でしたが、偵察機
の不足に応じて例外も多く生じました。
ポーランド戦線に参加した14軍の、航空偵察
部隊に対する1939年9月1日付けの命令を見ると
、偵察部隊の担当地域がまず示され、次に偵察
するべき地点、監視するべき道路や鉄道の区間
、注目するべき動き(鉄道からの荷下ろし等)
が指定されています。また戦術偵察機に対して
は敵の防御線の詳細情報を集めることが強調さ
れています。
着陸後、偵察結果は口頭で部隊司令官に伝え
られた後、簡単なメモ形式で必要な司令部に
転送されました。1939年9月22日のポーランド
戦線に於ける10軍の戦場偵察報告が
http://www.wwiidaybyday.com/に公表されてい
ますので一部引用します。
「Modlin北西と北東にドイツ軍、ポーランド軍
共に無し。晴天、高度15mで飛行したが対空砲火
無し。Modelinは放棄されたように見える。
西方のWeichsel川にかかる橋が破損、南東の橋
は損害無し。ModelinとWarchau間の路上と両側
に破壊された敵軍の装備あり。Warschau西方に
小規模の対空砲火あり。」
長距離偵察機の場合はこの後で詳細報告書が偵
察員により作成されました。戦場偵察や着弾観
測の場合は上述のように無線が活用されました
が、偵察結果も無線により逐次口頭報告されま
した。
空軍においては、偵察目的は爆撃部隊の
為の効果的な攻撃目標選択である為、敵拠点
毎の詳細情報を収集する必要が有り、複数の
拠点を結んでジグザグ状に飛行しました。
目的が異なるため、両者の偵察区域が重複する
場合がありましたが、止むを得ない事と考え
られ、むしろ情報の交換によって質を高める
努力が成されました。
☆初期の使用機材
本節も参考文献4のp27からp36に基づいて
います。
戦術偵察に用いられた初期の機材として
He45,He46が有り、これらは陸軍の仕様書
に基き1930年に設計されたもので、WW2
開戦時には航続距離の不足と対空砲火
に対する弱さが判明していました。
後継として開発されたHs126は1938年に生産
に入り、全金属構造で地上でシェルター
に格納する必要が無くなりました。
また防弾や無線、航法の装置が強化されて
不十分ながら夜間と悪天候時の作戦も
可能でした。しかし夜間偵察に関する課題
が完全に解消されたのはFw189が就役した後
のことでした。
Hs126の生産は進まず、He45、46からの
置き換えがほぼ終了したのは1940年以降でした。
また東部戦線において敵戦闘機との遭遇の
機会が増加すると、損害が増加しましたが
が補充が不足してStaffelが運用する機数は
徐々に減少し、予備機の確保も不可能に
なりました。
生産遅延の主な理由はKoluftを設ける時期が
比較的遅く、Lwの内部での発言力が小さかっ
た事と、戦争の早期終結が信じられて
いた事にありましたが、攻撃兵器(つまり
爆撃機や地上攻撃機)の強化に力を取られて
いた事も否めません。
初期の長距離偵察に採用されたのはHe45で
したが、代わる高速偵察機としてHe70
が提案されましたが乗務員からの下方
視界が悪いことから広く使用されず、
WW2開戦時にはDo17PがKoluft直属の
長距離偵察機として配備されていました。
1941年以降、長距離偵察に用いる機種は
Ju88Dに置き換えられました。
ポーランド(東西の国境の距離約600km)
及び西部戦線(独仏国境からパリまで約
400km)で、長距離偵察機の性能は十分で
したが、東部戦線が拡大してソ連軍が東方
へ大きく退くと効果的に偵察活動を行う為
には航続距離は大きく不足し(モスクワ
からウラル山脈まで直線距離で約1500km
有るのに対してJu88Dの航続距離は約3000
km)ソ連軍の動向に関する情報不足が原因
で陸軍の攻勢が失敗する事態が生じました
。また冬季の悪天候も偵察活動の困難の
一因であり、1942年11月のソ連軍の反攻の
際も十分な情報収集を行うことが出来ず
にStalingradでの6軍が包囲される失敗に
つながりました。
☆1942年以降の組織編制②-2-7
大戦中期以降の作戦地域の拡大の為に
GendLwbObdHが全体の指揮を執ることが
困難になり、また機材の損耗が著しい為、
偵察部隊として十分な機数を維持する事が
不可能となりました。更にKolutの任務が、
一部Flivo(後出:Fliegerverbindungsoffizier)
と重複する事も手伝って、実情に適合した
組織の見直しが行われました。
1942年2月に陸軍と協力する全ての偵察任務
をLwが直接実行することとなり、GendLwbObdHは
42年5月16日付けで廃止されました。
新たに陸軍参謀本部付けのder Generals der
Luftwaffe beim Oberkommando des Heeres
(GendLwbOKH)が置かれましたが、GendLwbObdH
がObdL直属だったのに対して、GendLwbOKH
はChefGenstに所属し、rankもKoluftと
同格のGen.Maj Guenter Lohmannが
任命された事から、参謀本部同士の相互
連絡が主要任務だったと考えられます。
その後約1年の間にKoluftは徐々に廃止され
、偵察Gruppenは
Nahaufklaerungsgruppe(従来の(H)が所属)または
FernAufklaerungsgruppe(従来の(F)が所属)
として再編成されました。
The Luftwaffe,1933-1945のReconnaissance
unitsのsectionを見ていただくと、(H)Staffel
がX/NAGrに名称変更された状況が
分かります。各GruppenはFliegerkorps
またはFliegerdivisionに所属しましたが、
陸軍との協力任務の他にFlKpsやFlDiv
の作戦の為の情報収集も担当し、また従来
Koluftに所属するスタッフから伝達された
戦術偵察情報は、Flivoを介して陸軍側に
伝えられる事になりました。
この事で陸軍との協力作戦の状況は大きく
変化し、以下の利点をもたらしました。
a陸軍協力部隊と、Lw直轄部隊の偵察任務の
重複を避けることができた。
(但し長距離偵察に関しては、上記の任務
の目的の違いから、任務の一本化は実現せ
ず、陸軍上層部は空軍向けとは別の長距離
偵察活動を要求しました。)
b戦力の効率的運用が可能になった。
c機材の補充が円滑になった。
d偵察部隊を一本化することで飛行場直属の
支援部隊の負担を軽減できた。
それまでのKoluftの困難な状況が想像され
ますが、新たな問題として以下の2点が
じました。
a各Armeekorp及びPanzer division毎に
一個Staffelを割り当てることが不可能
になった。
b機材がGruppeの拠点に集結された為、
陸軍部隊から距離的に離れる事となり、
緊密な協力関係の維持が困難に
なった。
☆中後期の使用機材
Fw189は戦術、戦場偵察機として開発されたもの
のGeneralstabから速度の不足を指摘されま
したが、密閉型キャビンによる乗務員の行動の
容易性、優れた下方視界、双発による信頼性の
高さ、後方銃手または通信を担当する三人目の
乗務員が乗り込むこと、高い通信能力により夜
間運用が可能であること等の長所が認められて
採用に至り、1941年の独ソ戦開戦の頃から配備
が開始され、高評価を得ました。しかし1942年
以降ソ連戦闘機の活動が強化されるとHs126と同
様に昼間の作戦行動は困難になりました。
その後戦術偵察においても比較的航続力の大き
い機体が必要とされ、Bf110等の双発機が導入さ
れました。
一方戦場偵察においては敵の攻撃により多く晒さ
れることから新規に高速の機体がどうしても必要
となり、結局小型の単座戦闘機に写真撮影装備を
施こすアイディアが採用されてBf109GやFw190Aの
偵察機型が生産されました。当初、操縦士が偵察
員を兼ねることから実戦価値が疑われましたが、
実際は高速性や運動性を生かして敵戦闘機や対空
砲火からの回避が容易な為に好評を得、専任偵察
員が必要な弾着観測や特定ポイントの詳細な確認
等を除く、大部分の任務に用いられました。
各部隊毎のこの時期の機種配備状況が下に有り
ますのでご覧下さい。
(The Luftwaffe,1933-1945)
2-3.空軍長距離偵察部隊
(続く)
②-2-1参考文献5:p247
②-2-2参考文献 Bundesarchive Verbindungsorgane der Luftwaffe
http://www.bundesarchiv.de/bestaende.php?BestID=1875
②-2-3参考文献6:p99
②-2-4参考文献4:p27
②-2-5参考文献4:p25
②-2-6参考文献4:p75-p83
②-2-7参考文献4:p101-p105
2-4.爆撃部隊及び地上襲撃部隊
☆爆撃部隊の基本理念
Luftwaffeが大規模な作戦を実施する際に
緒戦に行うべき事項は、
敵国の空軍力の破壊と制空権の獲得
でした。これにより陸軍部隊が敵国空軍
からの脅威に曝される危険を最少にすることが
でき、作戦上の大きな自由を獲得できます。
またLuftwaffeの損害も最少にとどめる事が
できると考えられていました②-2。
ポーランド戦線とフランス戦線及び初期の
東部戦線はこの原則に則って成功しました。
一方、Battle of Britainに当たって、
RAFの無力化を試みましたが、成功せず
結局作戦全体が失敗に終わりました。
☆電撃戦の発展
Luftwaffeの陸軍に対する作戦協力には
大別して二種ありました②-3。
1)特定地域の封鎖及び交通の遮断
indirect support
2)敵部隊への直接攻撃
direct support
Luftwaffeは伝統的には1)を重要視して
おり、空軍力により周囲から遮断した敵戦力
に対して陸軍が決定的な打撃を与えることが
基本戦術とされていました。
2)は決定的局面における特例的な戦法と
されていましたが、スペイン戦争で
von Richithofenが急降下爆撃機に
による陸上部隊への直接支援を成功
させました。この戦訓がWW2での
「電撃戦」に繋がるわけですが、
ポーランド戦開始時には、戦法として
未確立で、Luftwaffe自身が後方の
軍需工場への攻撃の効果の大きさとの
比較判断をしかねている状況でした。
しかしここで、装甲部隊に対する
急降下爆撃機による直接支援が
予想外に大きな成果を上げたことで、
ドイツ軍全体がこの理論に傾斜し、
オランダ、フランス戦で完成する事に
なります②-4。
「電撃戦」の完成に当たっては実戦
でのRichthofenの貢献は極めて
大きく、局地的な地上作戦の状況の変化に
空軍が対応するために(つまり、戦局上
最も有効な目標選択や誤爆の防止等の
目的で)彼は空軍司令部を直接協力
する陸軍指令部に隣接させて設置する
事をしばしば行いました。TOPの異なる二つ
の組織の協力が当初から成功したのは、彼の
官僚的でない実務運用の成果と言われて
います②-5。
「電撃戦」の理論とは,敵部隊を前線後方
の(水平)爆撃によって孤立させ、これに
装甲部隊と急降下爆撃部隊が協力した
集中攻撃をかけて短期で壊滅させること
ですが、ドイツがこれに傾斜した理由の
一つに短期勝利の追求が、日本と同様の
資源小国であったドイツの状況に合って
いたことを忘れるべきでは有りません。
☆東部戦線の膠着
WW2においてドイツ軍は西部戦線で
電撃戦により大きな成果を達成しましたが、
東部戦線では、1941年には優勢な局面を
作り出しながら、戦力の不足が原因で
決定的な打撃を与える事ができませんで
した。英国の戦後の評論で
「複数の相手国が連合を組んで対抗し、
攻撃するべき戦略拠点が多数ある場合
には効果的でない。」といわれた通り
に成って行きます②-6。
1942年以降は、戦線が拡大し過ぎて戦力の
集中が不可能となり、数量的に優勢なソ連軍
に徐々に反撃を許す事になります。
その結果Luftwaffeの作戦は量的に劣勢な
陸軍部隊に対する局地的なdirect supportが
大部分を占め、戦局全体を勝勢に導く
力を失います②-7。
逆に双発爆撃部隊迄が陸軍の前線の直接
支援に回らざるを得なくなった結果、最前線
で犠牲を払って敵戦力をいくら破壊しても
後方でソ連軍の自由な補給を許すような
不合理が発生しました②-8。
1943年以降、攻撃部隊としての急降下爆撃
部隊はJu87の旧式化と共に解散し、
戦闘爆撃機を用いたschlacht(地上攻撃)
部隊として再編成されます。
☆戦略爆撃の試み
Deichmannによれば空軍の任務として、
敵国の軍需工場や首都への攻撃等のstrategic
operation等も規定されており②-10、内部的に
戦略爆撃を軽視していた訳で無い事が
分かります。
事実1943年から44年にはKortenによりソ連の
軍需工場を攻撃する(戦略的)作戦が提案
されています②-11。
Deichmann自身も現有機種を集中運用により
、それを実行するべきだったと考えており
(効果は疑問ですが)、陸軍の局地作戦への
直接支援への過度の傾斜を非効率的だった
と言い切っています。②-12
軍事的に見て妥当性の高い作戦行動を採用
できなかった最上層部の判断の誤りがあったと
言うことでしょうか。
☆組織面の問題
彼は大戦後半にLuftwaffeの作戦行動が制約
されたもう一つの理由として、陸軍のHeeres
Gruppeの作戦区域に各Luftflotteが完全に対応
付けられており、そこでの地上戦支援の全面的
責任を負わされていた事を上げています
②-13。問題を解決するためには部隊の
根本的再編成が必要でしたが、実行される
ことはありませんでした。
また1942年以降Luftwaffenkommandoが
地上軍の直接支援の機能を受け持つことに
なりましたが、これについて別項で述べ
ます②-14。
②-1参考文献4:p20
②-2参考文献4:p109
②-3参考文献4:p114
②-4参考文献3:p30,p35
②-5参考文献4:p146
②-6参考文献1:p53
②-7参考文献4:p198
②-8参考文献4:p199
②-9参考文献4:p24,25
②-10参考文献4:p20
②-11参考文献1:p240
②-12参考文献4:p171
②-13参考文献4:p207
②-14参考文献4:p27
3.最高意思決定の仕組み
☆前書き
Luftwaffeの最高意思決定の問題は大きな
テーマで、WW2のドイツ敗戦の一因と
さえ言われていますが、ここでは主に
参考文献1に基づいてご紹介します。
☆WW2迄の組織変化
1934年のVersaille条約の見直しによりドイツに
国防軍の存在が正式に認められました。
海軍に関して、1935年6月1日に最高司令部として
OKM:Oberkommando der Marineが設立され、陸軍
にも1936年1月11日にOKH:Oberkommando des Heeres
が設置されました。しかしGoeringの影響が強かった
Luftwaffeには当初そのような組織が設けられず、
RLMがその役割を果たしました。
GoeringはReichsminister der Luftfahrt und
Oberbefehlshaber der Luftwaffeと称し、彼に
対する軍事的助言組織としてder Generalstabが
RLMの内部に有りましたが、民間航空を管理
する組織で有るRLM内部に軍事組織を設置した
ことは無理があり後の大きな確執の原因となり
ました。
(注:OKLと言う組織はこの時期存在せず、実際にその
名称の組織がLuftwaffeに成立したのは1944年以降で
した。多くの資料にLWの最高司令部として
当初からOKLが存在したように書かれているのは
誤解あるいは便宜的なものですが、そうなった理由
は以下のように推定します。
①OKMとOKHが早くから存在したことによる類推
②OKLと総称される組織はGeneralstabとInspektion
が一体になったものですが、そのようなものを
考えると説明に都合が良い。
③恐らく日本に於ける一番大きな理由は、海外の有力
ないくつかの参考文献にそう書いてあること。)
当初はvon BlombergがReichskriegminister
(国防大臣)とOberbefehlshaber der Wehrmacht
(国防軍最高司令官)を兼務して一応、内閣が軍に
命令する形式になっていました。
この仕組みに明確な変化が生じたのは1938年2月4日
で、国防省が廃止されて新たに設置されたOKW
(Oberkommando der Wehrmacht)の責任者となった
Wilhelm Keitelに国防大臣の機能が移行しました。
またHitler自身がOberbefehlshaber der Wehrmachtに
就任して軍に対する直接命令権を持ちました。彼は
は既にFuehrerとして政策や基本戦略の決定権を
持っていたので、この時点でHitlerの戦争遂行の意思
をOKWが現実化するシステムができ上がった訳です③-1。
☆OKWと各軍の関係
OKWはHitlerの署名した命令書に基づき三軍を指導して
命令を執行し、各軍はその下に作戦面の協力と実施を
進めました。
(下図ご参照願います)
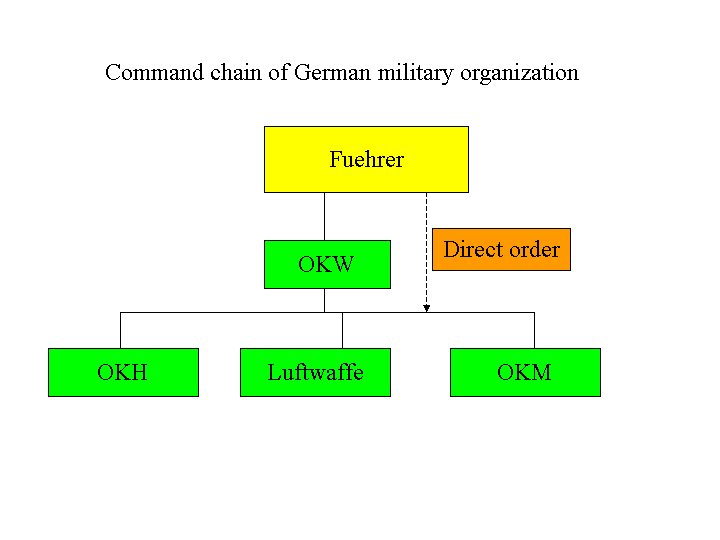
このように、全体戦略の為に三軍を指導調整べき
OKWでしたが、佐官級以上の派遣者の数が、陸軍の約
500人に対して、空軍と海軍は其々その1/5と少なく、また
Chef des Wehrmachtfuhrungsamtes im OKW (作戦指導部長)
だったAlfred Jodlが陸軍出身だった為、結局作戦上の
重要な意思決定は陸軍中心となりました。③-2
☆戦争指導の実際
WW2開始当初は、OKWは全体戦略や戦時経済の立案、
宣伝、情報面を担当し、具体的な作戦実行は三軍に
任されていました。しかし1941年の冬の対ソ連戦の膠着化
打開のため、Hitlerが同年12月19日にOberbefehlshaber
des Heeres(陸軍最高司令官)の地位に就いた以降、
東部戦線でOKWの指導的地位は失われ、OKHと並列的
にHitlerの戦争指導を補佐する立場に追い込まれました。
Luftwaffeから見れば、この変化は東部での陸軍に対する
直接支援作戦の一段の強化として跳ね返りました。
実際の戦争指導は以下の形式で進められました。
(1)Hitlerに対する報告会の席上での口頭指示を
OKWのスタッフが記録し正式に文書化して三軍
に連絡する。
(2)複雑で重要度が高い事項に関してはHitlerが
OKWのスタッフに検討指示を出し、スタッフが
関係組織との調整まで終了した案を、Hitler
に提案する。最終的にHitlerが承認した案を
Fuererentscheidung(総統決定事項)として
連絡する。
(3)特命事項は事前の調整を行わず結論だけを、
Fuererbefehl(総統命令)として連絡する。
これは必達事項として扱われました。
☆実務面の立案
最高意思決定がこのようになされた後に、実務上の
調整が伴う訳ですが、どのように行われたのでしょうか?
参考文献には「二つの事例が同じ方法で行われる事は
無かった。③-3」と書かれています。主にGeneralstabが
作戦に従事する部隊、陸軍との協力の方法、空軍の他の
部隊との協力の方法、前線への補給の方法等を指示し、
詳細はLuftflotteが決定しましたが、陸海軍
との協力の割合が大きい程、また関連するLuftflotte
の数が多い程、Generalstabの決定に基づく範囲が広く
なりました。
各軍の協力に関する立案段階の進め方に関して、
いくつかの例をご紹介します。
(1)ノルウェー作戦:作戦命令の公布以前に三軍の
幕僚によって、机上研究として具体的な各軍の
協力方法からスケジュールに至るまで、詳細
検討がなされていた。Hitlerの正式命令後
参加メンバーが中心となって、作戦が進められた。
(2)クレタ島作戦:Hitlerの意思によりクレタ島攻略
作戦が進められた。この場合Generalstabが立案する
ことが通例であるが、Goeringの介入により
Luftflotte4を中心に作戦を進めるように変更され
Jeschonneckが派遣されて立案した。
(3)Ardennes作戦:Hitlerのアイディアに基づき、
基本作戦をOKWが立案した。陸軍に関する
具体的命令はOberbefehlshaber West(陸軍)
が作成し、空軍に関してはGeneralstabの4人の
将校が作成してHitlerの承認を受けた。
Bodenplatte作戦は連合軍の航空戦力を憂慮する
Hitlerの意を受けて、途中Goeringが発案したと、
思われ、詳細計画をDietrich Peltzが中心に
なって作成した。
☆Goeringの問題
この項の最後にGoeringについて触れておきます。
彼は戦争が、Hitlerとそれを支える組織により
遂行されている現実を受け入れることができず、
自身とHitlerの個人的関係によりかかろうとしま
した。その結果、以下のような非合理な態度をとり
続けます。③-4
(1)Hitlerが毎日召集する戦況検討会を軽視して
しばしば欠席する。
(2)Hitlerと自分の間に他人が介在することを嫌い
OKWに自分の代理を派遣することを拒否する。
陸軍に唯一対抗できる力を持つ彼がこのような
姿勢であった為、LuftwaffeはOKWの内部組織で
「政治力」を発揮する事が、特に戦況が悪化した以降
困難になりました。また彼はHitlerの意思に
盲従的であり、しばしば感情的でエキセントリックな
命令を出した事は良く知られています。
Hitlerの側もGoeringの問題を認識しながら、
政権獲得以前から功労がある彼を排除する決断を
最後の段階まで避けました。③-5
独裁制度特有のこのような問題の数々が、政権の正しい
進路決定を妨げ、一つの国家の破滅にまでつながった
と言えます。
③-1参考文献1:p411
③-2参考文献1:p413
③-3参考文献1:p418
③-4参考文献1:p414,417
③-5参考文献1:p422
お気づきの点があったらご連絡下さい(直)。
ホームへ戻る