| H27.07.20. | 合 掌 造 り |
| 白 川 郷 合 掌 集 落 (世界遺産) |
| 梅雨明け直後の三連休の最終日は「海の日」でした。今までは天気が悪く雨降りを心配していましたが、梅雨明け直後の10日間は、天気が安定すると言われているので安心して白川郷へ行く事が出来ました。しかし天気が良過ぎて、気温は30℃を越える猛暑日になってしまいました。30℃を越えても名古屋の30℃と違い空気が乾燥しているので清々しさを感じ、陽射しを遮りながら見学して回りました。 |
| ●建造物の数 合掌造り建造物・・・114棟(内伝統的建造物指定109棟) 非合掌造り建物・・・329棟(内伝統的建造物指定8棟) 工作物・・・7件(鳥居、灯篭、石垣) 環境物件・・・8件(社業、樹木、水路等) ●人口約600人、世帯数約150軒 |
 展望台から見た白川郷集落。 |
| 白川村の合掌造りとは・・・・・ 「合掌造り」とは、木材を梁(はり)の上に手の平を合わせたように(合掌)山形に組み合わせて建築された、勾配の急な茅葺きの屋根を特徴とする住居で、又首構造の切妻屋根とした茅葺家屋です。屋根を急勾配にすることで、降った雪が積もらないと思っていましたが、地元の人の話では雪下ろしは必要だと教えてくれました。今年は積雪が多く3m程積もった時も有り、除雪には苦労したそうです。 |
|
|
| 白川郷合掌造りの変遷 |
 白川郷は、1995年に富山県の五箇山と共に世界文化遺産に登録された。合掌造りと言われるのは、屋根が手を合わせたような姿をしている事からその名がつきました。登録された白川村萩町には114棟の合掌造りの建物が残され、屋根は大きなもので3層~4層に分かれている。白川郷と五箇山地区には、年間200万人越える人が観光客として訪れている。 白川郷は、1995年に富山県の五箇山と共に世界文化遺産に登録された。合掌造りと言われるのは、屋根が手を合わせたような姿をしている事からその名がつきました。登録された白川村萩町には114棟の合掌造りの建物が残され、屋根は大きなもので3層~4層に分かれている。白川郷と五箇山地区には、年間200万人越える人が観光客として訪れている。今から55年程前の1960年頃、白川郷には200棟近くの合掌造りの家が有りました。昔の家族構成は50名を越える大家族が暮らしていた事も有り、明治42年の調査では男31名、女32名からなる大家族が実在していた記録が残っている。何故60名を越える大家族に成ったかと言うと、白川郷のしきたりで結婚しても分家が許されず、人々は働き手として家の中でカイコを育て、田畑を耕して暮らしていた。 しかしそうした伝統的な暮らしに変化が起きたのは1967年でした。岐阜県の北部飛騨地方は、高さ3,000m級の白山連峰等の険しい山々に取り巻かれ、長い間川に橋はなく、カゴの渡しが使われていた。加須良集落と言うと所では、農業で充分な収入が得られなくなり、人々は次々と都会に出て行きました。正業とした養蚕等が衰えるにつれて、大家族制度も今は遠い昔話に成りました。白川郷でも多くの集落で深刻な過疎化が進み、今は合掌造りを合わせても僅かに34人と昔の1戸あたりの人数に成ってしまいました。 高い山々に囲まれた周辺では、この地形を利用したダム建設が盛んに行われた。建設作業員が一時的に移り住んで来て、最盛期には人口約3,000人の村に9,000人もの関係者が入り込み盛況でしたが、ダムの完成と共に作業員や関係者が居なく成り、いつしか町は廃墟に成りました。ダム建設は村人に多くの変化をもたらしました。新建材のトタンやセメント等の建築資材が流入し、メンテに手間のかかる合掌造りに変わり、こうした材料で家を建てる人が増えました。白川村の中心部には立派な舗装道路が走り、色とりどりのトタン屋根が目立ち、役場や学校の建物も近代的なビルに生まれ変わりました。白川村では合掌造りの素朴な味わいを生かして、観光に新しい進路を開こうとしています。しかし個人の家に生活権をしばりつける事も出来ません。トタン屋根に変わるのも時代の流れによるものなのでしょうか。 |
 カゴの渡し |
 「ムカデ」カヤを滑り下ろします。 |
|
 1982年岐阜県白川村萩町の合掌造りの家は3分の2程に減っていました。一方で合掌造りの保存運動も行われて来ました。そうしたなか村人による合掌屋根の葺き替えが行われた。合掌造りの家はおよそ50年に一度屋根の葺き替えが必要です。屋根葺きには多くの人出が必要な為、昔から村人総出で行われて来ました。使うカヤは昨年の秋に山で刈り取り、その大きな束を積もった雪の上を滑らし3月に降ろします。村の人達はカヤの滑り落とす様子を「ムカデ」と呼んでいます。 1982年岐阜県白川村萩町の合掌造りの家は3分の2程に減っていました。一方で合掌造りの保存運動も行われて来ました。そうしたなか村人による合掌屋根の葺き替えが行われた。合掌造りの家はおよそ50年に一度屋根の葺き替えが必要です。屋根葺きには多くの人出が必要な為、昔から村人総出で行われて来ました。使うカヤは昨年の秋に山で刈り取り、その大きな束を積もった雪の上を滑らし3月に降ろします。村の人達はカヤの滑り落とす様子を「ムカデ」と呼んでいます。最近神田家の屋根の葺き替えが行われました。朝6時、ナワの架け直し始まります。骨組の中心となる合掌材とその補強の為、横に通してある「ヤナカ」という丸太を縄で締め付けて行きます。材木を縛るには「メソ」と呼ばれるマンサクの若木が使われます。「メソ」は白川村の山の至る所に生えている粘り気の非常に強い木です。メソは縄で縛り難い丸太どうしを縛るのに使います。合掌造りの屋根には釘は一本も使いません。メソは予め先半分だけねじり回して、柔らかくしておきます。半分だけ柔らかくすると言うのがメソを使う秘訣です。メソは丈夫で絶対に手で引きちぎることは出来ません。横に並ぶ「ヤナカ」と縦に並ぶ「クダリ」という丸太をメソで結び付けて行きます。開始から2時間後屋根葺きが始まりました。萩町の殆どの人が手伝いに来ています。この日は総勢230人にも成りました。参加した人は全て無料奉仕です。 |
 白川村には昔から「結」(ゆい)とう制度が有ります。一家の大仕事には互いに人出を出し合い助け合う事になっています。しかし次第に村人総出の葺き替えは行われなくなり、「結」の心が薄れて来ました。合掌屋根の葺き替えの時期は田植え前の4月から始められ、その屋根葺きの10ヶ月前から準備が始められます。まず最初の寄り合いは親戚を中心に村人が集まります。屋根葺きは一世一代の大仕事なので、屋根葺きの仕切り役を皆に承認してもらう大切な儀式なのです。屋根葺きの記録は過去の「結帳」に記載されています。手伝いに来てくれた人の名前が数百人に渡って残らず示されている。過去の例から必要な人数が割り出される。仕切り役は人集めから材料集めに至るまでの一切を仕切ります。人集めには集落の一軒一軒を回って屋根葺きのお願いをしなければなりません。これを「結願い」と言う。屋根葺きを二カ月後に控えた頃から「結願い」を開始する。兎に角天候に関わらずお願いに回るが、一番心苦しいのは、合掌造りに住んで居ない人へのお願いだ。毎晩「結願い」を終えて人数を検討する日が続く、お願いしても本当に来てくれるかどうかは当日フタを開けて見るまでは分からない。不安な気持ちを押し隠しながら兎に角「結願い」を続けるしかないと言い聞かせるのだ。 白川村には昔から「結」(ゆい)とう制度が有ります。一家の大仕事には互いに人出を出し合い助け合う事になっています。しかし次第に村人総出の葺き替えは行われなくなり、「結」の心が薄れて来ました。合掌屋根の葺き替えの時期は田植え前の4月から始められ、その屋根葺きの10ヶ月前から準備が始められます。まず最初の寄り合いは親戚を中心に村人が集まります。屋根葺きは一世一代の大仕事なので、屋根葺きの仕切り役を皆に承認してもらう大切な儀式なのです。屋根葺きの記録は過去の「結帳」に記載されています。手伝いに来てくれた人の名前が数百人に渡って残らず示されている。過去の例から必要な人数が割り出される。仕切り役は人集めから材料集めに至るまでの一切を仕切ります。人集めには集落の一軒一軒を回って屋根葺きのお願いをしなければなりません。これを「結願い」と言う。屋根葺きを二カ月後に控えた頃から「結願い」を開始する。兎に角天候に関わらずお願いに回るが、一番心苦しいのは、合掌造りに住んで居ない人へのお願いだ。毎晩「結願い」を終えて人数を検討する日が続く、お願いしても本当に来てくれるかどうかは当日フタを開けて見るまでは分からない。不安な気持ちを押し隠しながら兎に角「結願い」を続けるしかないと言い聞かせるのだ。170軒を回る「結願い」は屋根葺きの直前まで続いた。大屋根葺きの当日の朝、「結願い」をして回った村人のうち一体何人が来てくれるのか?。その不安を吹き飛ばすように、村の人を中心に中学生から、全国に呼び掛けたボランティアの人が350人を越えていた。この屋根葺きで一番技術を必要とするのは、屋根の形を整える「葺き士」だ。合掌造りの屋根の形は次に葺き変えるまでの間、何十年も残るからです。 この日は女性達も活躍しました。それは屋根葺きを手伝ってくれた人に出す食事です。親戚と近所の女性達およそ40名が2,000食の準備に追われていた。かつてはこうした仕事を通して女性たちはお互いを知り「結」の心をはぐくんできたのです。この日は総勢500人のお手伝いになりました。多くの人が無償で手を貸してくれる、人と人との繋がりの素晴らしさを痛いほど感じるものです。お手伝いが増えると結帳の記録係は大忙しになります。人の助けに成りたいと言う一人一人の気持ちを大切に書き記します。 暮らしと合掌造りを共に守り続ける為には不可欠な結の心、厳しい現実に生きる村人達は其々の思いを胸に村の絆を確かめ合うのです。 この13年間で屋根葺きは48軒有りましたが、殆どが業者が行いました。それでも結の心をつないでいきたい思いから、7軒の屋根葺きが住民参加で行われました。業者が行う屋根葺きは人と人との繋がりはないが、「結願い」や「結帳」の煩わしさは無い。しかし合掌造りを末永く継承して行くには業者の仕事では、この先危惧されるとの思いの人も居る。 |
 日本有数の豪雪地帯に有る白川郷。合掌屋根は釘やカスガイを使っていないのに、何故雪に押しつぶされないのか?屋根の角度は60度、正三角形の力学的に最も安定した形です。この屋根の角度が60度の傾斜と言うのは、一気に雪を落とす事が出来るのです。合掌造屋根の雪は1mに成ると一気に雪を落とします。この形も、豪雪地帯で暮らす先人達の知恵なのです。それにしても1mの雪に耐える合掌造りの屋根には、一体どれほどの重さが掛かっているのか?屋根の面積は、両面でおよそ400㎡。雪が1m積もった場合、全体では何と152tの重さが掛かっている計算です。これは大型ジェット機1機分の重さです。これ程までの重さに耐える事が出来るのは、建物にかかる力をうまく逃がす合掌造りの構造に有るといいます。 日本有数の豪雪地帯に有る白川郷。合掌屋根は釘やカスガイを使っていないのに、何故雪に押しつぶされないのか?屋根の角度は60度、正三角形の力学的に最も安定した形です。この屋根の角度が60度の傾斜と言うのは、一気に雪を落とす事が出来るのです。合掌造屋根の雪は1mに成ると一気に雪を落とします。この形も、豪雪地帯で暮らす先人達の知恵なのです。それにしても1mの雪に耐える合掌造りの屋根には、一体どれほどの重さが掛かっているのか?屋根の面積は、両面でおよそ400㎡。雪が1m積もった場合、全体では何と152tの重さが掛かっている計算です。これは大型ジェット機1機分の重さです。これ程までの重さに耐える事が出来るのは、建物にかかる力をうまく逃がす合掌造りの構造に有るといいます。合掌造りの特徴は、下の人が生活するジク組の部分と、屋根から上の三角部分が構造的に分離しているので、屋根荷重に対してもうまく逃げる形状になっている。合掌造りは1階に屋根が乗っかっている構造です。繋ぎ目は釘等で固定している訳では有りません。繋ぎ目は材木の先端を細く削りハリに差し込んであるだけです。この先端部分を「コマジリ」と言います。屋根の重さが集中する「コマジリ」。ここに屋根を支える秘密が有ります。屋根を固定して重量をかけて行くと、屋根の材木が僅かに横にずれますが、「コマジリ」に同じ重量を加えると、固定した場合は横にずれましたが、「コマジリ」の場合は僅かに下方に沈むのです。柱は縦方向の力には強く、横方向の力には弱い性質を持っているのです。「コマジリ」は縦方向に流した力を柱がしっかりと受け止める為安定するのです。こうした工夫により合掌造りは雪深い中でも、長い間持ちこたえる事が出来たのです。 |
|
|
 放水訓練 |
合掌集落での恒例一斉放水訓練 世界遺産の合掌造り集落で知られる白川郷(岐阜県白川村萩町地区)で、H24年11月4日、消防用の放水銃による一斉放水訓練が行われた。 午前8時にサイレンを合図に59基の消防用放水銃から約30mの高さに上る一斉放水が見事な光景を醸し出した。紅葉した背景に合掌造りの鋭く尖った建物に向けて、水柱の放物線がカーテンのように集落に降り注いだ。この訓練で放水銃の角度などを調整し火災等に対して被害を防ぐのです。 この訓練は毎年行われ、白川郷が一望出来る高台にある展望台では、見物客やカメラマンが最高の場所を確保しょうと、夜明け前から賑わっています。普段放水銃は格納されていて、滅多に見る事は有りません。皆様も見学される時には、格納場所を探してみるのも新しい発見として面白いのではないかと思われます。 |
 駐車場から「であい橋」を 渡り、観光を行います。 |
 駐車場 |
|
| 駐車場は何箇所か有りますが、料金は1回500円です。公共駐車場「村営せせらぎ公園駐車場」に停めます。「村営せせらぎ公園駐車場」は観光案内所・トイレを完備しており、駐車料金の一部は世界遺産の保存に活用されます。混雑の際は、係員が「寺尾臨時駐車場」や「みだしま公園駐車場」へ誘導します。白川郷は車両進入制限が午前9時から実施されますので注意が必要です。 |
 この村落に限らず他にも合掌造りのこうした建物は見られますが、白川では「切妻合掌造り」といわれ、屋根の両端が本を開いて立てたように三角形になっているのが特徴で積雪が多く雪質が重いという白川の自然条件に適合した構造に造られています。 |
 5年前に白川郷を訪れた時は、かやぶき屋根がもっと多かったのだが、今回見てかやぶき屋根の少なく成った事に落胆した。このまま減り続けると世界遺産で無く成るのではないかと危惧した。 |
|
| 合掌造りの建物は南北に面して建てられおり、これは白川の風向きを考慮し、風の抵抗を最小限にするとともに、屋根に当たる日照量を調節して夏涼しく、冬は保温されるようになっています。 合掌造りが日本の一般的な民家と大きく違うところは、屋根裏(小屋内)を積極的に作業場として利用しているところです。幕末から昭和初期にかけ白川村では養蚕業が村の人々を支える基盤産業でした。屋根裏の大空間を有効活用するため小屋内を2~4層に分け、蚕の飼育場として使用していました。 今は、民宿をしたり、みやげもの店や飲食店、家屋内の見学等も生計の一助になっています。 |
| この集落の特徴は又首構造の切妻茅葺屋根という屋根の形態です。日本の茅葺民家の屋根形態は入母屋造りか寄棟造りが一般的ですが、合掌造りは茅葺でありながら切妻造りです。この形にはやはり養蚕が大きく関わっており、切妻の開口部で風と光を取り込むことで蚕の飼育に適した環境が作り出されています。生活の為の機能が家の形となっていて、それが偶然にも合掌造りの美しさを感じる事が出来るのです。 |
 和田家 |
和田家住宅(重要文化財)合掌造り民家として最大級。 和田家は、天正元年(1573)以来、代々弥右衛門を名乗っていたことが知られ、江戸時代には明主や牛首口の番所役人を努めるとともに、白川郷の重要な現金収入源であった焔硝の取引によって栄えた。 和田家住宅は、白川村荻町伝統的建造物郡保存地区内の北部に位置し、西に面する主屋を中心にして、前方右手に便所、後方左手に土蔵が建つ。屋敷の周囲には、石組の消雪溝や池を配し、主屋の北側に屈曲する石組溝と池からなる庭園を設け、その北に石垣と防風林を備える。建築年代は不明であるが、主屋・土蔵・便所とともに江戸時代中期の建築と考えられる。 和田家は質の高い建築であり、式台付の玄関を備えるなど格式の高い造りとなっていて、世界遺産白川郷の合掌造り集落を代表する民家である。 |
 どぶろく祭りの館 |
 白川八幡宮 |
| 相 倉 合 掌 集 落 (世界遺産) |
| 白川郷の駐車場で、愛想の良い駐車料金徴収員の話によると、五箇山に有る相倉集落へ行くには高速道路を使うより、ここから一般道を走っても20分ほどで行けるので大差は無いと教えてくれた。一般道は車も少なく左右に積雪した景色を見ながら、快適なドライブでした。 相倉駐車場は1回500円でした。 |
 原始合掌造り (天地根元造り) |
相倉の合掌造り・・・・ 1995年12月、ユネスコの世界遺産一覧表に文化遺産として登録されました。相倉には20棟(住民約60名)の合掌造りが現存していますが、約100~200年前のものが多く、古いものには四百年前に建造されたものも有ります。 屋根の勾配は急で六十度。断面は正三角形に近く、雪深い地方の対策で、雪が滑り落ちやすい構造なのです。 この大きな屋根を支えるのが、根元が曲がった「チョンナ」と呼ばれる太い梁です。斜面に生育した自然に曲がったナラの木を用いています。又、合掌の組み立てには釘は一切使わず、縄とネソと呼ばれるマンサクの木を使っています。屋根の葺き替えは15年~20年毎に、森林組合が中心になって行われています。 |
|
| 越中五箇山相倉集落・・・ 五箇山は、庄川上流と支流利賀川の深い谷間に点在する七十の集落(旧、平村、上平村、利賀村)の総称で、相倉はその典型的な集落の一つである。五箇山には古くから人が住んでいたが、史料の上ではっきりするのは浄土真宗が広まってきた十五世紀末頃である。天文二十一年(1552)十月二十七日付けの「五箇山十日講文書」には大部分の集落が記されており、その中に相倉道場(現、相念寺)の坊守図書了歓の名もある。 合掌造りは豪雪に耐えるために六十度正三角形に造られた急傾斜の屋根を持つ。アマ(屋根裏)で蚕を飼ったため、切妻として明かり取りを設け、床下で煙硝(鉄砲火薬の原料)の土を培養したため床が高い。養蚕・煙硝・紙すきは江戸時代の五箇山の三大産業で、これらの生産と厳しい環境への対応から合掌造りが生まれた。 こうした貴重な遺産を守るために集落全域が文化財に指定され、ここに住む人たちも保存のために努力している。 文化財指定の経過・・・・ 昭和45年12月4日 国史跡に指定 平成6年12月21日 重要伝統的建造物郡保存地区に剪定 平成7年12月09日 世界遺産に登録 |
 |
 絶景ポイントから見た相倉合掌集落 |
| 秋篠宮同妃殿下御来訪のこぼれ話・・・・・ 秋篠宮様は、民宿で「私は、世界で三箇所好きな所が有りますが、その中の一つが五箇山です。」と仰られたそうです。そしてお泊りになった宿の思い出帳に「9年前は一人で来ました。今回は二人で来ました。この次は子供を連れて来たいと思います。」とお書きになり、宿を御立ちになったそうです。 |
 |
 |
| 上平村の合掌民家 雪深い五箇山では、藩政時代から明治中期にかけて、盛んに合掌造りの家が建てられました。急勾配の屋根は、雪が自然に落ち、高層の造りは、豪雪の時でも二階、三階からの出入りが可能です。土間や二階、三階のスペースは、かつて養蚕や製紙、塩硝などの生産場に利用されました。 家の内部は、一階の一部が土間で、一部はオエ(居間)としていろりを設け、残りは作業場や寝床として使っていました。入り口の片隅に炊事場、もう一方の片隅に小便所があり、普通大便所は屋外に別棟として設置してありました。五箇山では家族の寝室をチョンダ(帳台の意味)といい、オエの床よりも約十三cmほど敷居を上段にしてあるのが特徴です。 |
| 菅 沼 合 掌 集 落 (世界遺産) |
| 相倉合掌集落から五箇山ICへ向かう途中に、菅沼合掌集落が有ります。ここは一般道の上から集落が見えるので、集落全体を把握する事が出来ます。 駐車場も完備されていて、1回が500円です。駐車場の傍にはエレベーターが有るので、これを利用すると往復がとても楽です。 |
| この集落はカヤ葺切妻合掌造りの家屋が14軒あり、昔のまままとまって保存されている数少ない合掌集落です。合掌造りは礎石の上に大角柱を建て、桁や梁を渡して、その上に丸太の大合掌を組み上げカヤ葺とし、内部を2階、3階としたものである。建物は冬季の積雪に耐えるように建築されているので、角柱や桁や梁は太い材料を用いられているものが多い。 現存する合掌住宅の古いものは、天保年間(1830~1840)以前の建築から、新しいものは大正14年に建築されたものがある。 合掌集落は昭和30年代頃までに急速に姿を消し、ついに合掌集落の原型を永久に窺うことができなくなるので、その保存をはかるため昭和45年12月、この菅沼集落を国の史跡に指定したものである。平成7年12月には世界文化遺産に登録された。 また、この集落には民家を利用し、民族史料を展示する五箇山民俗館と煙硝の館を設置し、一般公開しています。 国指定史跡:昭和45年12月4日指定 |
 菅沼集落。 |
 |
|
 緑の草木が目を癒してくれました。 |
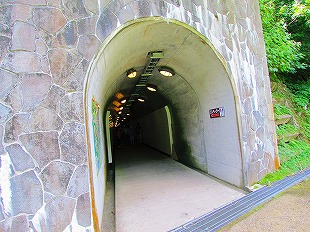 エレベータまでは綺麗なトンネルを通ります。 |
|
| |